
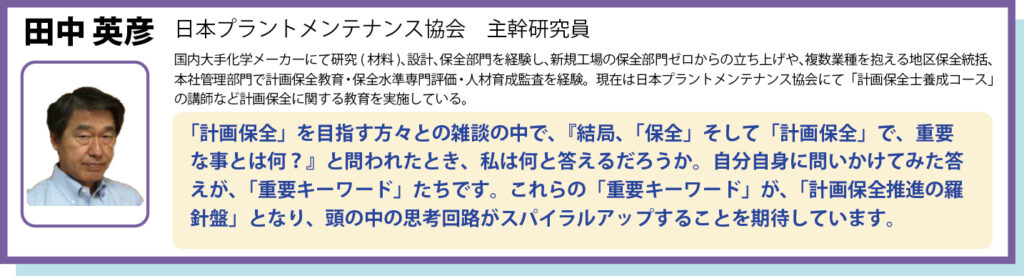
羅針盤その7 「長期の視点」
保全では「長期の視点」も重要だ。
筆者が企業に出向いた先で、「長期計画」を立てていないとの回答に驚かされることがある。
担当者は入れ替わることがあったとしても、殆どの装置産業界では、装置はその場所で長期に稼働し続ける。設備の将来を見据えての、長期計画を立案するのも、装置に接し・装置の状態に最も詳しい保全メンバーの責務である。
投資計画は別の部門が最終判断する場合でも、投資タイミングの技術的根拠を考え得るのは、保全にしかできないはずだ。
「計画保全」では、10~20年を想定した長期計画を立てることを推奨している。法定検査の周期や機器の更新寿命を踏まえての考え方だ。また、立てた計画の定期的な見直しも必要である。
設備ビンテージ(=年齢)との言葉を用い、設備の老朽化が整理されている。モノを大切に使う国民性なのか、設備の老朽化は深刻である。これまで、“宝”と位置づけ積み重ねてきた各々の装置の検査履歴をもとに、劣化を技術的に判定するのも、保全の大きな役割だ。
「長期の視点」を常に意識し、物事を判断しよう。
●重要参考テキスト
・『MOSMS実践ガイド』(p159:長期計画、日本プラントメンテナンス協会)
・「計画保全士養成コーステキスト」(p158:長期計画、日本プラントメンテナンス協会)
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。


